グローバルアンチパスバックで共連れ対策を図るアクセスコントロール
不正な入退室を防止するアクセスコントロールシステムは、重要な情報を守るため建物内部の安全性を高めます。不正侵入の一例として多く取り上げられる共連れは、アクセスコントロールシステムに求められるセキュリティ課題のひとつです。共連れ対策にアンチパスバックやグローバルアンチパスバックといった機能を、適用したアクセスコントロールシステムはセキュリティ強化に役立ちます。共連れ対策が施されたアクセスコントロールシステムは、情報セキュリティ管理における機密性の向上を図ります。
◎アクセスコントロールシステムにおける共連れ対策の課題
建物の内部空間に不審者や部外者が侵入するのを防ぐ対策手段として、アクセスコントロールシステムを用いたセキュリティ管理の導入は年々増加しています。紙媒体だけでなくパソコンやスマホを使った重要データを扱う機関において、電子機器の盗難や情報漏洩は致命的な損害を被る可能性があるためです。入退室権限のある人物のみが出入り可能なアクセスコントロールシステムの導入には、電子機器の盗難や情報漏洩などのリスクを低減させる目的があります。アクセスコントロールシステムを用いて部外者の不正侵入をいち早く発見するとともに、被害損失の拡大を防ぐよう管理には迅速な対応が求められます。アクセスコントロールの導入が普及する以前では、警備を配置した目視による確認が一般的でした。しかし、不正侵入を摘発するノウハウの継承は難しく、警備にあたる人によって監視レベルの差が出る可能性も含んでいるため、必ずしも安全とはいえません。警備員によって万全な管理体制を整えるには人手やコストも多くかかることから、安定して管理が行えるアクセスコントロールが必要とされています。人手やコストを抑えた共連れ対策を行うには、検知可能なアクセスコントロールシステムの構築が重要です。ピギーバックとも呼ばれる共連れにはさまざまなシチュエーションがあり、その多くは2つのパターンに分けられます。ひとつはアクセスコントロールシステムを通過できる人物に後続して、同時入室を行うパターンです。これは後続してくる人物に入退室権限が付与されているかどうか、不明な場合もあるため自然にアクセスコントロールシステムを突破されてしまう恐れがあります。もうひとつは、入退室権限をもつ人物が故意的に第三者を招き入れるパターンです。意図して不正侵入を画策しているため、非常に悪質なパターンですがアクセスコントロールシステムの突破に、このようなリスクを秘めていることは否めません。不正侵入を防止するだけでなく、コスト削減や人手不足などの課題解決にも有効なアクセスコントロールシステムの需要は、年々高まっています。

◎アクセスコントロールで構築するグローバルアンチパスバックの仕組み
不正侵入である共連れ対策に、グローバルアンチパスバックと呼ばれる方法があります。グローバルアンチパスバックとは、アクセスコントロールシステムによる正式な認証手順を踏まない限り部屋への入退室が行えない対策方法です。部外者や内部からの不正侵入を防ぐグローバルアンチパスバックは、複数の部屋が存在する広いエリアでの共連れ対策に適しています。グローバルアンチパスバックを導入するためには、共連れ対策を施すフロア設計図の作成が重要です。アクセスコントロールに用いられる認証機器を出入り口の両方に設置し、グローバルアンチパスバックを作動するための認証手順を作成します。グローバルアンチパスバックを施工した具体例としては、グローバルアンチパスバックが施されたフロアへ入室するには、まず1つ目の扉で認証を行います。入室したフロアには6つの部屋があると仮定します。その場合、1つ目の扉を含めて合計7つの扉が存在することとなり、入退室をするにはそれぞれの扉での認証履歴が必要です。たとえば、1つ目の扉で認証を行い入室したあと、2つ目の扉に入るには再度入室認証を行わなければなりません。退室時には、改めて2つ目の扉から退室認証を行い、1つ目の扉に戻って退室の認証を行う流れになります。これは残り3~6つある部屋の扉についても同様です。1つ目の扉を通過できたからといって、すぐに別の部屋へ入れるわけではありません。仮に2つ目の扉を突破して部屋に侵入できたとしても、退出時には入室時と同様に認証を行う必要があります。それぞれの扉で認証が行われていない限り、1つ目の扉から退出することはできません。さらに堅牢性を高める方法としては、2つ目の扉から入室認証を行ったあと、部屋の奥にも別の部屋があるとします。この奥の部屋を7つ目の扉と仮定した場合、部屋へ入室するにはこれまで通り認証が必要です。万が一、2つ目の扉で入室認証を行わなかった場合には、7つ目の扉での入室許可はおりません。正式な認証手順を踏むことで、7つ目の扉から入室が可能になります。退出時も同様に7つ目の扉から退出認証を行い、2つ目の扉、1つ目の扉といった流れで認証が必要です。
◎アンチパスバックとグローバルアンチパスバックの違い
アクセスコントロールシステムにきかれる共連れ対策には、アンチパスバックとグローバルアンチパスバックがあります。呼び名が類似しているため、混同されがちですが共連れ対策を行う手順や範囲が異なります。アンチパスバックと呼ばれる共連れ対策は、特定の扉の出入り口のみに設定し運用する方法です。建物のメインとなるエントランスに、アンチパスバックを施したアクセスコントロールシステムを導入することで、不正な入退室を防止します。入退室権限をもたない人物が共連れにより不正侵入した場合、退室時にも必要となる認証方法を知らなければ、侵入したフロアからは出られません。退出できない不審者を防犯カメラや警備員が発見したのち、該当の人物をとらえることが可能になります。アンチパスバックを適用したアクセスコントロールシステムは、マンションのセキュリティ管理や受付に人を配置しない宿泊施設などに適しています。複数の部屋がある広いエリアをまとめて管理できるグローバルアンチパスバックは、企業や政府機関などの情報セキュリティを強化します。複数箇所に設置された認証機器で正しい入退室認証が必要となるため、広いエリアでのアクセスコントロールシステムに有効です。複数回の認証が必要なグローバルアンチパスバックを、アクセスコントロールシステムに組み込むことで部外者の不正侵入をいち早く検知します。どちらも共連れを防ぐという意味では共通していますが、アクセスコントロールシステムで共連れ対策を行う際は、セキュリティ管理を行うエリアの確認が必要です。またアンチパスバックやグローバルアンチパスバックの、どちらを適用するのか検討することも重要です。一元管理可能なアクセスコントロールシステムに、アンチパスバックやグローバルアンチパスバックを施すことは、管理に要する人員コストの削減にも貢献します。

◎アクセスコントロールにグローバルアンチパスバックを導入方法
アクセスコントロールで共連れ対策を行うには、グローバルアンチパスバック機能が搭載された認証機器を選ぶことが大切です。グローバルアンチパスバック機能のある認証機器を選ぶことで、追加コストをかけることなく共連れ対策が可能になります。共連れ対策可能なアクセスコントロールシステムを構築するには、認証機器についてのアドバイスがもらえる施工業者を選ぶことも必要です。アクセスコントロールシステムの構築に、どのような認証方法で共連れ対策を行うかを施工業者に相談できなければ、運営に支障をきたしかねません。これまでの入退室管理に多く活用されていた認証方法は、カード認証や暗証番号を用いたアクセスコントロールシステムの構築でした。しかし近年ではカードの譲渡や暗証番号の流出リスクがあることから、アクセスコントロールに導入する認証方法の見直しを行うケースが多くみられます。生体認証の認知が高まるなか、アクセスコントロールシステムの認証に身体の一部を用いた方法が広く取り入れられているのも、そのためです。顔認証や指紋認証といった生体認証は、直接的な他人への譲渡ができないため、より強固な共連れ対策を施したアクセスコントロールシステムの構築が実現します。また施工業者にはグローバルアンチパスバックの認証設計を行ってもらえるか、事前に確認しておくこともポイントです。区間ごとのセキュリティレベルを設定することも大切ですが、アクセスコントロールシステムをどう組み立てていくかは専門業者との相談が必要になります。たとえば一般の従業員も利用する会議室に、高度なセキュリティ管理が求められるサーバールームのようなアクセスコントロールシステムは不要です。不要なグローバルアンチパスバックの設計によって、一般従業員が多数のエラーを発生させてしまうような状況では適切な対策ができているとはいえません。サーバールームや役員室といった、厳密なセキュリティ管理が必要な場所でのアクセスコントロールシステムに、高度な共連れ対策を施すことで空間の堅牢性を高めます。
◎アクセスコントロールシステムで共連れ対策を行うメリット
アクセスコントロールとグローバルアンチパスバックで、二重のセキュリティ管理を施すことによりレベルの高い共連れ対策が実現します。部外者が共連れで侵入した場合、複数回の認証を行う手順を知らなければ、それぞれの部屋に入退室をすることはできません。厳密な情報セキュリティ管理が必要なエリアに、共連れ対策を施したアクセスコントロールシステムの導入は効果的です。アクセスコントロールに用いられる認証機器のなかには、標準でグローバルアンチパスバックを備えた認証機器もあるため、別で機材を導入する必要がありません。顔認証を用いた認証方法は、共連れ対策を行うアクセスコントロールシステムの構築に最適です。顔認証は画像データで認証状況を確認できるだけでなく、顔検出機能によって共連れを検知する機能が搭載されるため、不正侵入を未然に防ぎます。さらに顔認証やカード認証、暗証番号など異なる方法を組み合わせた、二要素認証が構築できる認証機器であれば、より高度なアクセスコントロールシステムが実現します。共連れ対策に有効な認証機器をアクセスコントロールシステムに用いることで、別の機材を導入することなく管理が行える点はメリットのひとつです。グローバルアンチパスバックによって不正侵入が検出された際には、管理責任者に通報が入るよう設計しておけばスピーディな対応が可能になります。グローバルアンチパスバックによって強化されたアクセスコントロールシステムは、警備に要する人員コスト削減にも貢献します。一元管理が可能なアクセスコントロールシステムは、不正侵入をいち早く発見するだけでなく正確な現場の状況確認に有効です。
◎共連れ対策を施したアクセスコントロールシステムの導入事例
セキュリティ管理を行うアクセスコントロールで共連れ対策を行うには、エリアの設定や認証手順の設計が大切です。グローバルアンチパスバックの適用によって入退室制限をかけたアクセスコントロールシステムは、部外者の侵入を防ぎます。
○銀行のセキュリティに共連れ対策をしたアクセスコントロールを導入
多くの個人情報や重要情報を扱うセキュリティ管理エリアに、グローバルアンチパスバックを適用したアクセスコントロールシステムを構築しました。アクセスコントロールの認証方法には共連れを検知する顔認証を導入し、エリア内の堅牢性をより高めています。画像データで認証状況を確認できる顔認証は、不正侵入を発見した際の対応が素早く行えるためアクセスコントロールの導入にぴったりです。グローバルアンチパスバックの設計によって管理レベルを向上させるアクセスコントロールシステムは、警備に配置する人手不足の課題解決にも役立ちます。
○政府機関のアクセスコントロールにグローバルアンチパスバックを適用
重要情報や国家機密など厳重な情報管理を求められる機関に、グローバルアンチパスバックを適用したアクセスコントロールシステムを構築しました。複数回の認証手順が必要なグローバルアンチパスバックは、内部の人間による安易な入退室を許しません。さらにセキュリティレベルをあげるため、顔認証とカード認証を用いた二要素認証でアクセスコントロールシステムを運営しています。内部の人間が不正に侵入するのを防ぐアクセスコントロールシステムは、一元管理が可能なため管理者の業務負担軽減にも適しています。
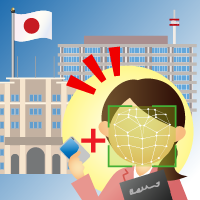
◎まとめ
情報セキュリティ管理の必要性が高まるなか、不正侵入である共連れ対策はセキュリティ管理における課題のひとつです。その課題をクリアするには、アンチパスバックやグローバルアンチパスバックを施したアクセスコントロールシステムの構築が欠かせません。共連れ対策に有効なアクセスコントロールシステムを構築するには、専門的知識をもつ業者への相談が大切です。部外者の侵入を防ぐアクセスコントロールシステムで、共連れ対策をご検討の際はKJ TECH japanへお問い合わせください。













